ワールドメイト代表深見東州先生は、宗教者としての弱者救済の立場に立った、慈悲と慈愛の実行。そして人道的見地に立った、社会への対応。また社会良識に基づく、誠実な対応という3つのスローガンに基づき、ワールドメイト以外の公益団体においても、さまざまな福祉、教育、スポーツ、学術、芸術の、公益活動を日本と世界で実践しています。
中国の辺境地区に、「春蕾小学校」130校建設
 総出で深見東州先生を出迎えてくれた子供たち。
総出で深見東州先生を出迎えてくれた子供たち。中国人との区別をつけるため、公式の場では、常に羽織袴を着用します。
中国は、北京・上海など沿岸の都会は、近年めざましい発展を遂げつつあり、西側諸国とほとんどかわらない、豊かな情報と富と物資に恵まれています。しかし、西部地域をはじめとする、目立った産業のない、地方の生活水準はきわめて低いのです。ちょうど、日本の明治時代や、終戦直後のような、極端な貧しさの中で、文化的な生活から取り残されています。こうした辺境地区には、家計の貧しさから、義務教育すら満足に受ける余裕がなく、小学校途中でやむなく自主退学し、働き始める子供も多いのです。
中国では、都市部のめざましい発展にともなって、地方との格差が年々深刻になりつつあります。辺境地方では学校自体の数も少なく、建物はあっても照明器具がなかったり、倒壊する危険の高い、老朽化した建物だったりします。そして、ふつうの義務教育を、当たり前に享受できない子供が、現在でも100万人以上いるのです。 そして、そのほとんどが、女子の子供なのです。

こうした現状を聞き、深見東州先生が会長を務める特定非営利活動法人 世界芸術文化振興協会(IFAC)では、中国の最貧地区に130校の小学校を寄付することを、中央政府の中国児童少年基金会、中国婦女連合会に申し出ました。
2000年4月から、向こう13年間で毎年10校ずつ、IFACの寄付により、中国児童少年基金会と地元の教育委員会の三者が協力し、130校の建設が始まりました。現在、130校はすべて完成しています。そして、このプロジェクトでは、校舎の建物を寄贈するだけでなく、学内の備品や1000冊以上の蔵書の図書館、またスライドやコンピューターなどの機材も提供し、ビジュアルで勉強できる設備も整えています。
 春蕾クラス同窓会(2007年4月)
春蕾クラス同窓会(2007年4月)その他、貧しい少数部族の30人の女学生を、北京で学ばせ、大学まで卒業させた「春蕾クラス」。また同じく、「樹人学校クラス」の30人。また、芸術クラスの30人などの教育もあります。その他、敦煌の100人孤児を育てるプロジェクトなど、様々な教育救済を行っています。
また、深見東州先生は、特定非営利活動法人 世界芸術文化振興協会会長として、「中国児童慈善家」として、中国国家より表彰を受けました。また、中国国家民政部より、「中華慈善賞」のベスト10人にノミネートされました。
オーストラリアン・シンギング・コンペティションを支援
 オーストラリアン・シンギング・コンペティション(1999年)
オーストラリアン・シンギング・コンペティション(1999年)「オーストラリアン・シンギング・コンペティション」は、オーストラリアで最も権威ある声楽コンクールです。このコンクールは、将来性のある声楽家たちを、大きく育てようという趣旨で行われ、奨学金の賞金総額は、9万オーストラリア・ドル(14種類の賞の総額)。
このシンギング・コンペティションは、今までに、素晴らしい歌手をたくさん生み育ててきました。ここで賞をとると、世界で屈指の先生に学ぶことができ、また世界のトップレベルの音楽家たちと、共演できるからです。まさに、このシンギング・コンペティションは、世界レベルの活躍への登竜門だと言えます。このコンペティションは、1998年からは、オーストラリアオペラ協会と特定非営利活動法人、世界芸術文化振興協会(IFAC)の共催で行われています。
オーストラリアン・オペラスタジオ(AOS)
 オーストラリアン・オペラスタジオ〔略称:AOS〕
オーストラリアン・オペラスタジオ〔略称:AOS〕IFACでは、世界的なバリトン歌手グレゴリー・ユーリシッチ氏と共同で、西オーストラリア州パース市に、「オーストラリアン・オペラスタジオ(Australian Opera Studio〔略称:AOS〕)」を設立しました(2002年開校)。同校の生徒は、音楽大学卒業のレベル以上の実力をもつ、新進アーティストたちです。このオペラスタジオは、本当に才能と可能性ある彼らを、さらに、世界の一流舞台で通用する、トップアーティストに育てるのです。そのために、実演オペラやコンサートを通して、プロの実力を育てる教育機関です。これは、世界でも類を見ない試みとして、各国の音楽関係者から注目を集めています。
世界三大テノールの一人、プラシド・ドミンゴ氏が、名誉総裁に就任しています。このスタジオの模様は、MXテレビで詳しく紹介されました。卒業生は、すでにイギリスのコベントガーデン他、世界一流のオペラハウスの団員となり、大活躍しています。
ブラインドゴルフ(盲人ゴルフ)

深見東州先生は、23年前の1988年に、日本で最初に盲人ゴルフ倶楽部を設立し、日本に紹介した「日本のブラインドゴルフの父」として知られています。
ブラインドゴルフは、ベトナム戦争における、米国の傷痍軍人のメンタル・リカバリーのために始まったものです。そして、現在では英語圏を中心に、活動は世界的に広がっています。日本には、現在250人以上のブラインドゴルファーが育っており、2年に1回、各国持ち回りでワールド・チャンピオンシップが開催されています。1996年には、日本でワールドチャンピオンシップが開かれ、NHKほか多くのテレビや新聞、雑誌で紹介されました。深見東州先生が設立し、名誉会長を務める特定非営利活動法人日本ブラインドゴルフ振興協会(JBGA)では、それらを全て主催しています。また、支援の輪は世界に広がり、深見東州先生の呼びかけにより世界盲人ゴルフ協会(IBGA)が、1998年に設立されました。そして深見東州先生は、皆に慕われて総裁に就任したのです。
また2006年のブラインドゴルフ・ワールド・チャンピオンシップは、再び日本で開催されました。このように、日本と世界で、23年間もブラインドゴルフを支援してるのです。
シニアゴルフの振興とゴルフインストラクターの育成
ゴルフなどのスポーツの社会貢献を目的として、深見東州先生により、国際スポーツ振興協会(ISPS)が設立されました。
特に、障害者のためのゴルフやスポーツの振興、またシニアゴルフの振興、ゴルフ・インストラクターの育成など、積極的に支援しています。
平均寿命がますます伸びてる現代では、男性も女性も、楽しみと生き甲斐をもって人生を豊かにするには、ゴルフは最適なスポーツです。国際スポーツ振興協会(ISPS)では、男子シニアおよび女子シニアの大会を支援していますが、その大会のプロアマ戦には、必ずブラインドゴルファーを招き、盲目のゴルファー達に、あこがれの有名選手とプレーできる感動を与えています。こうして、シニアゴルフ全体にスポットを当てていますが、それは同時に、盲目のゴルファー達に夢と感動を与え、やる気と生きがいを与えるモチベーションにもなっています。
そして、「ゴルフの社会貢献」というテーマを掘り下げると、インストラクターの育成が不可欠となります。そのため、ISPSでは、インストラクターの育成と支援にも力を注いでいるのです。
女子シニアゴルフの振興
2003年、NPO法人 日本ブラインドゴルフ振興協会(JBGA)は15周年を迎えました。この記念すべき年に、“日本のセント・アンドリュース”と言われる、日本最古のゴルフクラブ神戸ゴルフ倶楽部で、JBGAのブラインドゴルフ大会が開催されたのです。
この年、神戸ゴルフ倶楽部はちょうど100周年でした。このとき深見東州先生は、神戸ゴルフ倶楽部の方から、「最初の100年はゴルフの普及。次の100年は、ゴルフの社会貢献」ということを聞き、非常に感銘を受けたのです。
それ以来、深見東州先生は神戸ゴルフ倶楽部のメンバーにもなり、ブラインドゴルフ以外にも、ゴルフの社会貢献の道を模索し始めました。そして、その翌年(2004年)、稲葉真寿美プロとの出会いがあり、女子シニアは試合に出る機会に恵まれてない、という実状を知ったのです。
50歳でシニアになる男子と違い、女子は45歳でシニアとなります。平均寿命がますます伸びてる現代では、女性が45才でシニア、男性は50才でシニアといっても、まだまだ若い盛りというプレーヤーも多いものです。しかも、シニアプレーヤーは年々増えていくのです。しかし、男性のシニア公式戦は、日本やアメリカや欧州にもありますが、女子シニアの公式戦は、当時は世界中でアメリカにしかなかったのです。
そこで、女子シニアゴルフの振興のために、深見東州先生の呼びかけで、米国のブラインドゴルフ協会をサポートしている、The LEGENDS Tour(米国女子シニアゴルフ協会〔WSGT〕)の協力を得て、米国女子シニアの公式戦を日本で行い、それを世界にオープンする大会を開催したのです。
こうして2005年4月、NPO法人 日本ブラインドゴルフ振興協会(JBGA)と、世界ブラインドゴルフ協会(IBGA)、 The LEGENDS Tour(米国女子シニアゴルフ協会〔WSGT〕)の三者共催で、「第1回ワールドシニアゴルフレディースオープン選手権」が、日本で開催されました。

翌年、2006年4月には、「第2回ワールドシニアゴルフ レディースオープン選手権」が、太平洋クラブ御殿場コースで行われ、再び世界殿堂メンバー達が来日しました。
女子シニアプロのバイタリティあふれる活躍や魅力は、ゴルフの面白さや可能性を広げ、アマチュアゴルファーのやる気や技術の向上にも役立ちます。そして、これらの大会は、いま活躍している女子プロ達の、将来の受け皿を作るものでもあるのです。
海外でのシニアゴルフの振興
海外では、深見東州先生が設立した国際スポーツ振興協会(ISPS)は、The LEGENDS Tourと協力し、2006年11月、オーストラリアで「HANDA AUSTRALIA CUP」を開催しました。(「HANDA(半田)」は、深見東州先生の本名)
これは、男子シニア、女子シニア、男子ジュニア、女子ジュニアが一緒に、ひとつのタイトルを争う世界初の大会です。シニアは、ジュニアに自らの熟練の技を伝え、ジュニアはシニアのすぐれた技術やゴルフへの姿勢、またマナーや経験智を継承する機会を得、非常に意義深い試合でした。そして、地元のマスコミからも、大変注目されたのです。
これら、世界の女子シニアゴルフへの貢献を評価され、深見東州先生はThe LEGENDS Tour(米国女子シニアゴルフ協会)のチェアマンに就任しました。日本人の男性が、米国で女子シニア協会のチェアマンになるとは、大変異例で素晴らしいことです。
男子シニアゴルフの振興
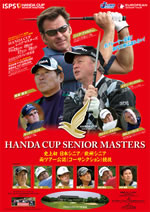 2010年「HANDA CUP SENIOR MASTERS」
2010年「HANDA CUP SENIOR MASTERS」


